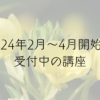インパチェンス (インペイシェンス)
フラワーエッセンス・インパチェンス(インペイシェンス)と共鳴する心
【インパチェンス (インペイシェンス)が助けになる人の経験しやすい傾向やパターン】
・衝動的で我慢強さがない。他者のゆっく りとしたペースにいらだつ傾向。「火」の要素が強すぎて緊張やいらいらが生じやすい。
【パターンのなかに内在されている目覚めようとしている性質】
・他者の活動のペースや自分の人生の流れを受け入れ、それと共に歩むことができる。
植物としてのインパチェンス(インペイシェンス)の特徴
ツリフネソウ科ツリフネソウ属 学名:Impatiens glandulifera 和名:オニツリフネソウ
インパチェンスはhimalayan balsam (ヒマラヤホウセンカ)とも呼ばれるヒマラヤ原産の植物です。水辺や湿地を好む一年草で、急速に成長して背丈は2mほどにもなります。開花期は7~9月です。花は上から吊り下げられる形になっています。花の形は独特で、よく観察しないとわかりません。
大きな特徴は、下萼片(かがくへん)が袋状になっていて、その先に距(きょ)と呼ばれる花冠(かかん)の基部が後ろに飛び出たものがあります。ここから蜜が分泌されています。ホウセンカと同じように、熟した果実にちょっと触れるだけで種を勢いよくはじきとばします。
この花の属名 Impatiens にはラテン語で「我慢できない」という意味があります。日本ではオニツリフネソウと呼ばれ、帰化植物として見られる地域があるようです。
インパチェンス(インペイシェンス)とツリフネソウ
一方日本に自生しているツリフネソウ属は、ツリフネソウ、キツリフネ、ハガクレツリフネ、エンシュウツリフネがありますが、植物のジェスチャーがインパチェンス(インペイシェンス)に近いのはツリフネソウのように思われます。
どちらも一年草で春に発芽して一気に成長して8月~9月に開花します。インパチェンスはオニツリフネソウと呼ばれるように2mくらいの草丈に成長しますが、ツリフネソウは80cmほどです。
花はとちらも3個の花弁と3個の萼片から構成されていて、とても複雑な形をしています。特定のマルハナバチが入っていくのにちょうどぴったりの形をした袋状になっているのですが、その部分は花弁ではなく萼片で、先端には距(きょ)と呼ばれる蜜を分泌する部分があります。
ツリフネソウ属の属名 Impatiens には「我慢できない」という意味があると書きましたが、日本に自生するキツリフネ( Impatiens noli-tangere )という黄色い花のツリフネソウの小種名 noli-tangere には「私にさわらないで」という意味があり、キツリフネの英語名はそのまま Touch-me-not です。
これらの名前は、熟した果実に少しでも触れると、果実が破裂して種子を弾け飛ばす性質に由来すると言われています。