フラワーエッセンスの植物観察を通して体験すること
フラワーエッセンスの植物観察
「植物観察会って何をするの?」
と思われる方もいらっしゃると思います。
フラワーエッセンスの植物観察で行うことは、植物の実際の大きさを測ったり、各部を丁寧に調べたりしますが、自然科学の観察とは違って、スケッチして、形や色をたどります。スケッチといっても、植物を芸術的にうまく描こうとしているわけではありません。
やりたいのは、観察しようとする植物がもっている形や色に注目して、できるかぎり丹念に再現してみることです。それを通して植物の形や色そのもの、植物そのものに出会うということをやろうとしています。
違いは意識のあり方
じゃあ、「普段は植物そのものに出会ってないの?」
と思われますよね。
「植物園に出かけて行って、たくさんの植物の花の写真を撮ってくるのと何が違うの?」
と思われますよね。
違いは意識のあり方です。
僕らが普段見ているのは、はたして「植物そのもの」でしょうか?
一般化された「赤」と今目の前にある「赤」
日常生活をしているとき僕らはたいてい左脳優位の状態ですが、左脳は見たものを分類して、一般化して、名前をつけて理解しようとするのが仕事です。
たとえば、この花は「赤い」花だと左脳が判断したら、この葉っぱは「ハート形」だと思ったら、「花そのもの」の赤を見るのをやめて、あるいは葉っぱ自体の形をたどるのをやめて、自分の知っている、頭の中の「赤」や「ハート形」に置き換えて、そうして花の色や葉っぱの形がわかったと思う。理解したと思う。これが僕らの中で普通に起っていることだと思います。赤には無限に赤があり、ハート型には無限にハート型があるにもかかわらずです。
植物観察では、一般的な赤ではなく、今目の前にある花の色を、一般的なハート型ではなく、今目の前にある葉っぱの形を体験しようとします。
普段左脳がやっている、比較したり、分類したり、一般化したり、判断したり…といったことを休めて、植物そのものの色や形を丹念にたどることをやりたいのです。
その経験は、普段僕らがどれほど、自分の思いこんでいる「赤」や「ハート形」に影響され、制限されているかを発見する経験になると思います。
「わかった」と思ったり、理論で解釈できたりすると…
普段左脳がやっている、比較したり、分類したり、一般化したり、判断したり、解釈したり…といったことを少しの間休ませて、植物そのものの色や形を丹念にたどることで、目の前にある植物そのものに出会う。というのがフラワーエッセンスの植物観察でやりたいことの一つです。
なぜなら、僕らは「わかった」と思ったり、理論で解釈できたりすると、もうそれ以上目の前の植物の色や形を丹念にたどること、言い換えると、感覚を開いて目の前の植物に意識を添わせることをやめてしまうのが普通です。
それはつまり、目の前の植物との対話をやめて、自分の主観や価値観の中に乱暴に植物を引き入れて解釈してしまうことになりかねません。
自分の世界を出て、感覚を開いて意識を添わせる
「植物そのものの色や形を丹念にたどることで、目の前にある植物そのものに出会うこと」を別の言い方をすると、「自分の世界を出て目の前の植物に、感覚を開いて意識を添わせること」だとも言えます。
植物との対話
そのような形で植物に向き合うことができたとき、
植物とつながることができたとき、
その時間は、
僕らが植物と共有している「生命」のもつ色や形を通して
植物と対話する時間になります。
植物と共有している「生命」を通して
僕らは植物と「生命」を共有しているのでその色や形を体験することを通して植物と対話することができます。
そのために、普段の左脳モードをちょっと休めて、色や形を丹念にたどることをやってみようということです。
これが植物観察のときに、植物を描くことを大事にしたい理由です。
自然の色や形を体験するとき、僕らの心はその色や形に応じて動きます。
その自分の心の動きを感じながら観察をすること自体が植物との対話になります。
そして、そうした心の動きは、その植物のフラワーエッセンスの作用と深い関連があります。
自分の世界を出て目の前のものに心を添わせること
このことを逆向きに見てみると、僕らは普段目の前のものに感覚を開いて心を添わせることよりも、自分の先入観や主観や価値観の枠の中で「解釈してわか(った気にな)る」ことを、いかに優先しているかということです。
フラワーエッセンスとは直接関係ありませんが、フラワーエッセンスの植物観察のときの、植物への向き合い方についてとても参考になる本があります。
『脳の右側で描け』ベティ・エドワーズ著 野中邦子訳 河出書房新社
この本はカリフォルニア州立大学ロングビーチ校で教鞭をとっていたベティ・エドワーズ氏が「絵が全く描けない人たち」が描けるようになるための学習プログラムとして開発したものが土台になっています。左脳が普段どんなことを行っていて、右脳モードになると、ものの見方や捉え方、知覚の仕方がどう変わるかということが体験できます。
『リンゴは赤じゃない』山本美芽著 新潮社
43歳で中学校の美術教師になった太田(恵美子)先生の教育法を取材したもの。「りんごは赤じゃない」というのは、
太田先生が子どもの先入観をなくすときに投げかける言葉。著者のコメント「…先入観をなくし、自分の目でものを見る力をつける。そのうえで自分だけの考えをつくり、表現する学習が、ゆるぎないプライドを生み、人間を驚異的に成長させていく現場を、私はこの目で見ることになりました。…」

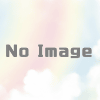



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません