フラワーエッセンスの性質と植物の関係:エルム
昨年の冬至から昨日の夏至までのSeeds of Angelicaの活動は、植物観察会を中心にかなり外的な活動を活発に行ってきました。ここからは活動の方向性が少し内的なテーマに移ると思います。2015年の前半の経験を内的に深めていく時期かなと思っています。その一つがフラワーエッセンス・リサーチプロジェクトで、もう一つが自分が経験したことを皆さんと共有することだと思っています。
昨年の冬至のころ僕が飲んでいたのはエルム(Elm)のエッセンスでした。エルムを例にフラワーエッセンスの性質と植物の関係、そしてその背景にある物語について書いてみたいと思います。どんな感じになるかなあ…。
フラワーエッセンス・エルムの性質
エドワード・バッチはTwelve Healersの中でエルムを必要とする人の典型的なタイプについて「立派な仕事をこなしている人で、人生の呼び声に従い、何か大切なことをしたいと望んでいます。しかもその行いのほとんどは人類の利益のためです。しかし、時折、自分の担った責務があまりに難しく、人間の力では及ばないかのように感じられ、落ち込んでしまうことがあります」(*1)と説明していますね。
普段僕らがエルムを必要とするのは、背負っているものの重荷に圧倒されて自分の能力に自信を無くし落ち込んでしまうようなときです。エドワード・バッチはエルムを「落胆、失望」のカテゴリーに分類していますから、エルムはただ自分の能力に自信が持てないというだけでなく、自分自身に失望したり、情けなくなったり、消耗してしまったりするパターンがあるときに助けとなるエッセンスですね。
エドワード・バッチはフラワーエッセンスの必要な精神状態を自ら体験し、その状態に癒しをもたらす植物を探し出していったといわれています。チェリープラムやエルムは、エドワード・バッチが残した38のフラワーエッセンスの後半の19に取りかかり始めたときにつくられたもので、1935年の3月ごろということになります。そのときのエドワード・バッチの心境を想像してみてください。翌年の11月27日に亡くなったわけですから、背負った仕事の重荷に圧倒されたとしても決しておかしくはないでしょう。また、そのことを念頭に置いてTwelve Healersのエルムの記述を読み返してみることもできます。エルムのフラワーエッセンスはまさにエドワード・バッチのこの時期の精神状態の助けになるものだったのだろうとHealing HerbsのJ.バーナード氏は述べています。(*2)
エルムの木とエルムの花
エルム(Ulmus procera)の木は小石川植物園にあります。幹の周囲を実際に計ってみると、ちょうど5mありました。J.バーナード氏は「エルムを初めて見た時印象に残るのは、どっしりとした大きな柱のような姿です(proceraは背が高いことを意味しています)。この巨大な柱のような幹は、成長すると30m以上の高さになることが多く、幹周りはおよそ5mになります。」(*2)とエルムを初めて見た時の印象を語っていますね。
僕が初めてエルムを見たのは12月の小石川植物園でした。すべて葉を落としていた時期で樹形全体の形がよくわかりました。なんといってもその立派な幹が印象的でした。同時に幹とは対照的に、どんどん分岐して先端ではとても細くなる枝の細やかさが際立っていて、その二つのコントラストが印象的でした。

そして、今年の3月8日の観察会の前日、エルムの木が花をつけた姿を初めて見ました。花が咲くと木全体の印象が変わります。エルムの花は高いところに咲くので間近で観察するのが難しく、しかも大きさも色も目立つような花ではないので、個々の花が開花しているかどうかを確認するには望遠レンズが必要です。けれども木全体の印象は、花が咲くとまったく変わります。冬の青い空を背景に立つエルムの姿はそれはそれで堂々として美しいのですが、花が咲くとその堂々とした感じに何か温度が加わるような、柔らかさが加わるような感じがしました。

『植物のかたちとはたらき』の中にも次のような記述があります。「花が咲くと、花の様子は力強い幹とは対照的です。ある著述家はエルムについて『エルムの花が3月に満開になると、木全体が陽光を浴びて暖かく輝く』と記しています。」(*2)
エルムの物語:「救い手」と等身大の自分
昨年の11月ごろから3か月間くらい僕はエルムのフラワーレメディーを飲んでいました。そして「軽く」なりました。どう軽くなったかというと、自分への無意識の期待に応えようとし過ぎなくなったように思います。

そのきっかけは、これまでも何度か経験してきた、「何やってきたんやろ。おれ。」という感じです。自分の役割や仕事をやり遂げることができないんじゃないか、自分には無理なんじゃないか、自分がやってきたことに果たして意味があったのだろうかと、自分を疑って落ち込むというパターン。
そういう自分と一緒にいることができたのはエルムのフラワーレメディーのお蔭だと思うのですが、その自分と一緒にいて見えてきたのが、自分は自分に何を期待しているのかということでした。人の期待に応えようとする傾向が自分は強いなと思っていましたが、それは結局「無意識の自分自身の期待」からなんだと気づいたのです。
じゃあ「無意識の自分自身の期待」というのはどこからくるのか。それは理想のヒーラー像であったり、「救い手」という普遍的なイメージにかかわるものなんじゃないか。そういう普遍的な「救い手」のイメージに強く影響を受けているんじゃないか。そう思ったのです。
思い返してみると、等身大の自分よりも、普遍的なイメージ(理想のヒーラー像)に影響されて、そのイメージと等身大の自分とのギャップに落ち込んでいたのです。
普遍的なイメージは個人が引き受けるには荷が大きすぎます。普遍的なイメージを引き受けすぎると、エドワード・バッチがエルムの解説に書いているように「しかし、時折、自分の担った責務があまりに難しく、人間の力では及ばないかのように感じられ、落ち込んでしまうことがあります」(*1)という状態になるのだと思います。
FESの『フラワーエッセンス・レパートリー』のエルムの解説の項に「自己を『英雄』や『救世主』の役割に当てはめて見ることを止め」という記述があるように(*2)、エルムタイプは「救い手」のアーキタイプの影響を受けているということですね。
利他的な志をもっていて、それを達成しようと果敢に振る舞おうとして個人的なことを超えて役割を引き受けてしまうような傾向にエルムのテーマは関連しているのだと思います。私たちが、なんとか力になりたいと思う時、心の深いところで「救い手」のアーキタイプば活性化します。援助者として活動する人にとって関連の深いテーマなんだと思います。
エルムのフラワーレメディーを服用しながら、そして実際にエルムの木に会いに行ったりしながらそういうことに気づいていきました。
そして、期待されているだろうと無意識に信じる役割に自分を沿わせたり、そういう役割をこなそうと苦闘する自分に気づいたときには、肩の力を抜いてリラックスして、できないことを手放して「個人的な」興味や熱意や軽やかさを自分の中心に置くようにしました。
自分の興味や熱意や軽やかさとつながっている信頼によって、仕事や役割を愉しめばいいんだとエルムは教えてくれるように思います。
————————
*1:ジュリアン・バーナード、マーティーン・バーナード 『Dr.バッチのヒーリング・ハーブス』 スミス・マキコ訳 BABジャパン 2003
*2:ジュリアン・バーバード 『バッチのフラワーレメディー植物のかたちとはたらき』 谷口みよ子訳 英国フラワーレメディー・プログラム 2013
*3:ジュリアン・バーバード 『バッチのフラワーレメディー植物のかたちとはたらき』 谷口みよ子訳 英国フラワーレメディー・プログラム 2013
*3:ジュリアン・バーナード、マーティーン・バーナード 『Dr.バッチのヒーリング・ハーブス』 スミス・マキコ訳 BABジャパン 2003
*4:パトリシア・カミンスキ/リチャード・キャッツ 『フラワーエッセンスレパートリー』 王由衣訳 BABジャパン 2001
ここまで読んでくださってありがとうございました。もし、何か参考になったり、この記事いいなと思われたら、💛のボタンを押していただけるとうれしいです。



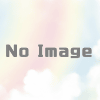





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません