フラワーエッセンスを選ぶときの二つの視点
フラワーエッセンスを選ぶときの二つの視点
一つは「何が問題か」「何が原因か」といった因果論的な見方。
もう一つはコンステレーションを見る視点。
コンステレーションは、コン(with)とステラ(stella:星)からできてる言葉で、もともとの意味は星が一緒になってできる星座のことですが、こころの内側の出来事と外的な出来事が、偶然なんだけれども「私」にとっての意味の重なりやつながりをもって、全体が一つの(星座のように)意味をもってくる現象のことをいいます。
因果的なものの見方
因果論的なものの見方は、科学技術をはじめとして、現代社会を物質的に物凄く豊かで快適なものにしてくれているので、ともするとその見方がすべてに通用するような錯覚に陥ってしまうことがあります。
因果論的なものの見方は客観性を重視して誰が見るかに関係なく、原因と結果の道筋を見つけることができます。それは「私」との関係を問いません。
たとえば、学校へいけない子がいて、そのことを因果論的に見ると、「その子が学校へいけない原因は何か」ということになります。そのとき、「私」はその事象の外側にいます。「私」は、その子が学校へ行けないこととは切り離されていて、関係のないところに立っています。
けれども、コンステレーションとなると、そうはいかない。「私」は全体の内側にいて、「私」の個性や、「私」の生き方が深くかかわってきます。その子が学校へ行けないことが「私」にとってどんな意味をもつのか。
子どもを学校に行かせるボタン
1992年、河合隼雄先生の京大退官記念講義「コンステレーション」をまったく偶然にテレビで見たときから、僕の中にずっと残っていることの一つは、「子どもを学校へ行かせるボタン」を探していないか?という自分自身への問いです。
まだ「不登校」という言葉もなかったころから故河合隼雄先生は学校へ行かない子どもさんと会われていたわけですが、実際に「・・・・うちの息子を学校へ行かせるボタンはどこにありますか?」と訊かれたことがあるそうです。(*1)
これは極端な例で笑ってしまいそうな話にも聞こえますが、そう簡単に笑ってられる話ではないと思います。考えてみれば、僕らは普段からほとんど意識しないで大抵のことをそんなふうに考えてるんじゃないでしょうか。
原因は何か?
問題は何か?
原因は何なのか?
それを突き止めて取り除いたり、変えたりすることができれば、結果をコントロールできるというのが因果論的な考え方です。もちろん、それがとても有益な答えを導き出してくれることを僕らは何度となく経験済みです。
生きていることは関係をもつこと
けれど、ここで問題となるのは、こうした因果論的な見方や考え方の対象が「生きている」ときです。
生きているということは互いに関係をもっているということで、関係をもっているということは、こころがかかわっているということです。
因果論的な見方は通常そこを不問にすること、つまり「私」との関係を切り離して自分を原因と結果の外側において道筋を見つけることで成り立ちます。外側にいればたいしてこころを使わなくて済みます。
ですが、生きているということは本来絶対に外側にはいられなくて、自分も現象の内側にいるということです。内側にいるときにはこころを使わなくちゃいけない。
「私」を内側においた全体を見る目
僕らは因果論的な見方、考え方の価値を十分に知っているからこそ、普段からほとんど意識しないでそれを使うんだと思います。その価値を認めたうえでのことですが、自分のことを考えたり、人のことを考えたりするときに、あまりに因果論的な見方に偏るのは得策ではないと思います。
因果論的な眼と同時に、「私」を内側においた全体のコンステレーションを見る眼をもつことが大切なのではないかと思います。
——–
*1:河合隼雄 『こころの最終講義』 新潮社 2013, p.72
読んでくださってありがとうございました。もし、この情報が何かのお役に立てたら、💚のボタンを押していただけるとうれしいです。


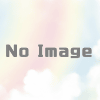


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません